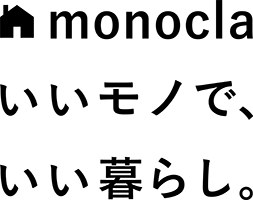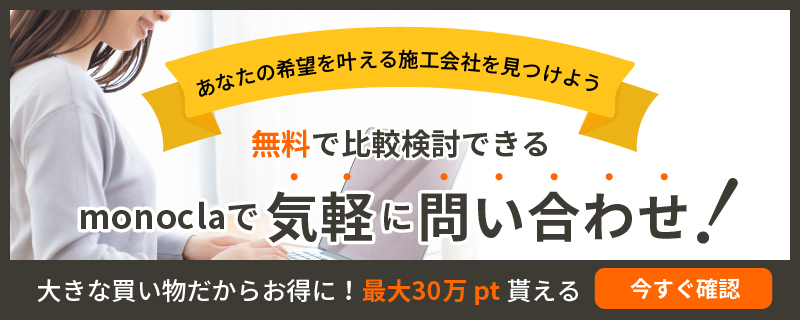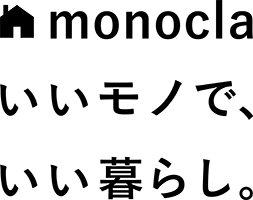住宅を購入するときには住宅ローン控除について知っておきましょう。というのも、住宅ローン控除を受けることができれば、年間に10万円単位の税金が控除される可能性があるからです。しかし、住宅ローン控除を受けるには条件があるので、この記事では住宅ローン控除の概要や条件について解説します。

住宅ローン控除の概要
まず、住宅ローン控除の基本的な事項である以下について解説します。
・住宅ローン控除の概要
・住宅ローン控除の期間と控除額について
・住宅ローン控除のシミュレーション
住宅ローン控除の概要
住宅ローン控除とは、住宅ローンの残高に応じて所得税から控除を受けられる制度です。つまり、支払い済みの所得税の還付を受けることができるということです。また、所得税から控除しきれなかった分は、住民税からも一部控除できます。
住宅ローン控除の期間と控除額について
| 最大控除期間 | 13年間 | |
| 年間控除額 | 1~10年目 | 年末のローン残高の1% |
| 11~13年目 | 以下のいずれか少ない方 ・住宅ローン残高or 住宅の取得価格(上限4,000万円)のうち少ない方の1% ・建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷2 |
上述のように、所得税から控除しきれない分は住民税から控除できますが、住民税から控除できる額は「前年の課税総所得金額の7%(136,500円限度)」が上限となります。
住宅ローン控除のシミュレーション
仮に、以下のケースで住宅ローン控除のシミュレーションをします。
・住宅ローンを組んで不動産を購入して5年目
・年末の住宅ローン残高が2,300万円
・納めるべき所得税が15万円
・翌年の住民税が17万円
まず、住宅ローン控除額は「年末残高2,300万円×1%=23万円」となります。ただ、納めるべき所得税が15万円なので、所得税を全額控除しても8万円(23万円-15万円)控除しきれません。そのため、その8万円は住民税から控除されます。
実際の流れは、会社員の場合は初年度だけ確定申告しますが、その後は年末調整で所得税が全額還付されます。また、住民税は返還されるのではなく、翌年の「支払うべき住民税」から控除されるという仕組みです。

住宅ローン控除を受ける条件
次に、住宅ローン控除を受ける条件について解説します。まず、借入(ローン)に関する条件を解説し、その後に新築住宅を購入する場合と中古住宅を購入する場合の条件について解説します。
借入に関する条件
住宅ローン控除を受けるための「借入に関する条件」は以下の通りです。
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下
・自己居住用の住宅取得が目的である
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・以下のいずれかからの借入である
-銀行
-農協・信用金庫・信用組合
-住宅金融支援機構
-地方公共団体
-各種公務員共済組合
-勤務先
特に、住宅ローンの返済期間が10年以上であるという点には注意が必要です。とはいえ、一般的には上記の条件をクリアしているケースが大半でしょう。
新築・中古住宅の住宅ローン控除の条件
前項を踏まえ、次に新築・中古住宅を取得するときに、共通している住宅ローン控除の条件を紹介します。
・住宅ローン控除を受ける人自身が住宅の引き渡しから半年以内に居住する
・住宅の床面積が50㎡以上
・上記と合わせて床面積の2分の1以上が自己居住用
注意すべきは「床面積が50㎡以上」という点です。この面積は登記面積であり、図面集や広告などに記載している面積と異なります。というのも、登記面積は壁の内側の面積(内法面積)であるのに対し、図面集などに記載している面積は壁の一部も含まれている面積(壁芯面積)だからです。
そのため、登記面積は図面集に記載している面積よりも小さくなるので、特に52㎡~55㎡ほどの住宅を購入する人は注意しましょう。図面集に記載されている面積が52㎡以下であれば、登記面積は50㎡を切っている可能性が高いです。
中古住宅の住宅ローン控除の条件
一方、中古住宅を取得したときには、前項の条件のほかに「一定の耐震基準を満たしていること」が条件です。その一定の耐震基準とは以下のいずれかをクリアしている必要があります。
・住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得している
・耐震基準適合証明書を取得している
・既存住宅売買瑕疵保険に加入している
・築年数が一定年数以下である
築年数が一定年数以下とは、木造で20年以下、耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)で25年以下になります。中古住宅購入時は、前項の条件と合わせて上記の条件についても確認が必要です。
まとめ
このように、住宅ローン控除は「年末のローン残高×1%」が返還される可能性があるので、住宅購入時の大きなメリットといえるでしょう。しかし、上述したように住宅ローン控除を受けるための条件があるので、その点をしっかり確認する必要はあります。